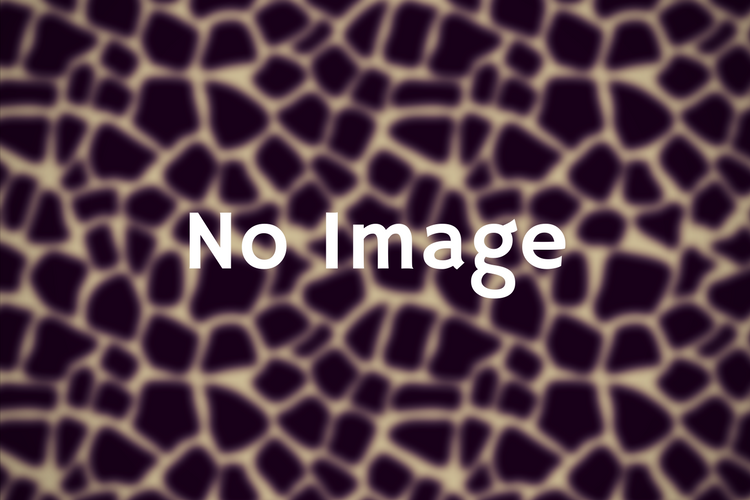「しんでくれた」のあらすじ!谷川俊太郎さんの絵本、食育には怖い?

絵本「しんでくれた」が怖い!
谷川俊太郎さんが著者で安心していたけれど、
これは子ども向けというよりちょっと大きい子や大人向けかも?
食べるために、命を落とした家畜がいる。
だから、有難く食べるんだ。
という内容です。
難しいテーマを描いた絵本。
谷川俊太郎さんの淡々とした詩と、塚本やすしさんの濃く力強い絵。
正直なところ、ちょっと食欲がなくなってくる気も…?
下記クリックで好きな項目へ移動!
絵本「しんでくれた」が怖い
絵本「しんでくれた」は、谷川俊太郎さんの詩からできている絵本です。
いきものは
いきものをたべなければ
いきていけません。
にんげんは
ほかのいきもののおかげで
いきているのです。
引用元 絵本「しんでくれた」
食卓に出されたハンバーグ。
食べながら、この肉のもとになった牛や豚や鶏に思いを巡らせる子どものお話です。
簡単な言葉で、子どもの視点から描かれています。
しかし、なかなかパンチが効いていて…。


真っ黒なページに、「しんでくれた ぼくのために」という言葉が重く響きます。
とても抽象的な絵にも見えるけれども、血や肉や骨を連想させるような赤と白。
牛の生きている感じや、生々しさや、苦しみを伝えたいかのような、力のこもった筆遣い。

でもまぁお腹は空くし、食べない訳にもいかないです。
おいしくいただいちゃいますよね。
男の子の表情がとてもあっさりしていて、重い言葉とのギャップがすごい。
でも、普段のほとんどの人間もこんなもの。


豚も、鶏も、いつも食べている肉なのだと伝えた後の、↓このページ↓

ヒィ…
画像を明るくしていますが、実際の絵本はもっと暗いです。
何だか、暗い家畜小屋に入れられて、亡くなってしまった者たちの嘆きのような絵。
嘆きというより、恨み?
「ぼくは人間で、人間を食べる動物はいない。
それにぼくがしんだら家族が悲しむから、食べた命のぶんも生きる」
と前向きな終わり方になっています。
食育の絵本として評価も高く、また谷川俊太郎さんの詩だからファンもいるのでしょう。
確かに、食べ物は色んな生き物からの命をつないでいますから、
この絵本はそれをストレートに伝える良い絵本。
世界に苦しんでいる人達の存在、戦争、環境問題。
これらと同じで、食事は命をいただいていることも、「目を背けてはいけない事実」。
想像力の豊かな子どもは、もしかしたら、
「動物にしんでもらってまで、食べなきゃいけないのかな?」
「自分が食べるようにしなければ、しななくて済んだかな?」
という考えに至る子もいるかもしれません。
実際に養豚場に職場体験に行き、その後、精肉所にも行き…
となったら、大人だってしばらくはお肉は口にできなくなってしまいそうですよね。
「ちゃんと全部食べようね」と持っていく食育というよりは…。
動物を食用として消費するのを極力減らそうと考える子もいるかも。
(別に菜食主義は悪いことじゃないので構わないですが)
絵本のレビューに「給食を残しがちな子に見せようと思います」と書いている人がいました。
もともと食べられない子にその対応では、食育として逆効果になる可能性もありますね。
食育は楽しく!
ついつい、大人の目線だと、子どもにはたくさん食べてほしいと思ってしまいます。
そして、食べさせたいがために、感謝の強要をさせてしまいます。
「作ってくれた人に悪いから食べなさい」
「食材になってくれた動物に悪いから食べなさい」
気持ちはとても分かります。
でも、食べる子どもの気持ちに寄り添いたいものですね。
子どもの気持ちを汲み取り、自発的に動けるようになるまで待つ、
大人にはそういう姿勢が求められます。
だって、大人なのですから。
どうしても食べなきゃいけないという状況は、
逆らえない立場の子どもにとっては苦痛です。
子どもに頑張らせる・子どもに我慢させて何とか食べさせる、
その前に大人がもう少し待ってあげてもいいですよね。
日本の飲食店で飲み放題プランがあると、
かなり多くの大人達が大量に食べ物を残して帰ります。
結婚披露宴で、どんなに高価な料理が出ても、残す人は大勢います。
(結婚式場でバイトしたことありますが、高級食材でもまるまる残されてます)
そして、恵方巻の時期になると、
コンビニで売れ残ったものが大量に廃棄され問題になります。
「完食は当たり前」「いただきますの挨拶は当たり前」
と教育されてきた大人達であるはず。
それなのにフードロスが社会問題になっていますよね。
完食指導の結果が、これでしょうか。
その状態で、子ども達には「感謝して全部食べなさい」と言うのは、説得力が全くない。
子どもに言う前にまず大人から行動しないと…と思わされます。
そもそも、まだ子ども。
しっかりしているように見えても、咀嚼力や嚥下力は、大人ほどありません。
食事を与えてやった側の気持ちを主張する前に、
まずは食べる子どもの気持ちに耳を傾けてほしいです。
関連記事 食育は楽しくなきゃ!学校の「完食強要」が訴訟に?!
↑この記事でも専門家が述べています。
個人差があり食べる量は違うのに、
一律に同じ量を完食するのが、学校の給食では当たり前でした。
「だから、大人は自分の食べられる適切な量を判断することができていない」のだと。
楽しい食育はまず「残しても大丈夫」だと安心させ、
リラックスした気持ちで食事に臨むことから。
そうでないと、食を好きになるきっかけすら奪ってしまうことになります。
- 子どもの食事量には個人差がある
- 好きなものと嫌いなものは、人間なので当然ある
- 食育の基本は、食事を楽しむこと
- 自分に合った食べ方を選べるようにする
現代の保育所では、これらは常識になっています。
子どもの気持ちを受け止め、
楽しくおいしいと感じられるようになってから、
そこから「命への感謝」を伝えていくのもいいですよね。
そうして、「残さないように頑張って食べる」のではなく、
「最初から自分の身の丈に合った食べ方をする」ようになることが望ましいのではないでしょうか。
谷川俊太郎さんってどんな人?
谷川俊太郎さんとは、絵本作家としても有名ですが、
詩人としても、翻訳家としても大活躍。
代表作はPEANUTS・SNOOPY。
シュールでチャーリーブラウンのらしさをよく表現された日本語訳をされています。
しかし、もっともっと、日本のほとんどの子ども達が知る作品があります。
それは、レオ・レオニーの名著「スイミー」!
優しくて、分かりやすい言葉で、谷川さんの絵本ってとても安心感があるんですよね。
子ども相手だからといい加減な言葉で誤魔化すことはせず、
子どもの人権を尊重して言葉選びをされているのだろうなぁというのがよく伝わってきます。
関連記事 児童労働がテーマの絵本「そのこ」!
貧困のために学校に行かずに働く、「児童労働」。
それをテーマに書いた絵本「そのこ」も、「しんでくれた」と同じ、
谷川俊太郎さんと塚本やすしさんのタッグによる絵本です。
重くて暗い、けれど向き合わなければならない問題を書いています。
「そのこ」も「しんでくれた」も、暗いと思われる部分を淡々と描くところが似ていますね。
まとめ
関連記事 情報社会の生き方が分かる!メディアリテラシーの絵本
谷川俊太郎さんの絵本「しんでくれた」
- 普段の食事は、動物の命をいただいて成り立っている
- 食べた動物の分まで生きたい
- 自分が亡くなったら、家族が悲しむ
ということを伝えてくれています。
フードロスを社会問題にさせてしまった大人こそ、
読んで食に向き合うのもいいのでは。
子どもにはまず、与える側の思いを押し付ける前に、
「楽しく食べること」から始めたいですね。