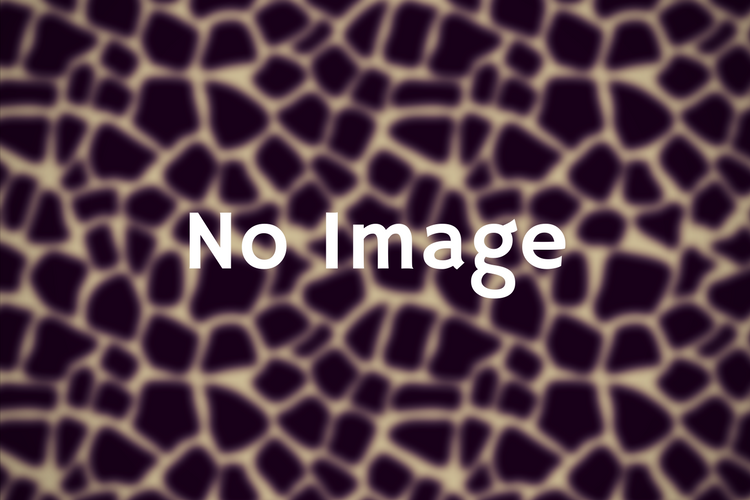トイトレの方法!イライラしないために、まずおまるで遊ぼう!

トイレトレーニングとおむつ卒業、どうしますか?
私が以前職場で、ベテラン副園長から教えてもらったこと、それは…
おむつ外れは夏が狙い目!だということ。
でもご安心ください。
冬でも、いつでもいいじゃない!
楽しく始めよう、トイレトレーニング!
下記クリックで好きな項目へ移動!
おまるでステップとは?

おまるでステップとは、コンビから発売されているおまるです。
何と、3wayなんです、ウェーイ!
始めはおまるとして使い、その後は補助便座として、そしてトイレや洗面台での踏み台として、子どもの成長に合わせて3役もこなしてくれるスゴイ奴です。
我が家で使っているのはこれです。
しかし、もっと検索してみると、5wayのおまるなんてのもありました。
あああ、アンパンマン大先生じゃないですか。
5wayってすごいポテンシャル。
こりゃ敵わんです。
小さい子は誰もが通る道のアンパンマン。
もはやアンパンマンはインフラです。
そのアンパンマンの音声で、おしっこができた時に褒めてもらえたり、ただ跨って遊んだりできるのって、めっちゃ仕事できるおまる。
ただ、音声が出るということなので、丸洗いはできないですね。
その点はコンビのおまるの方が扱いやすいでしょう。
我が家のおまる日記
産後間もない私はたまたま「オムツなし育児」というワードを知り、それを調べて何となくおまるを買ってみようかなと考えるようになりました。
そこで出合ったのがおまるでステップです。
さて、どのように家庭の保育に「導入」しようかな?と考えた私。
まずは遊ぼう
子どもが寝ている間に開封し、とりあえずリビングに置いてみました。
レッジョエミリアアプローチでいうところの「挑発」というものですね。
当時、生後8ヶ月くらいの我が子ぶどう氏。
見慣れないおまるを見つけると、新しいおもちゃだーと喜んで飛びかかっていきました。
うんうん、それでいい。
暫く観察していると、ぶどう氏はおまるを解体し、補助便座を手押し車にして遊び始めました。
うん、手を置く場所は合っている!!
まぁこんなもんでいいか…と自由に遊ばせました。
乗って遊ぼう
その後に、「乗って遊ぶこともできるんだよ」とヒントを与えるように、乗せてみました。
すると、これは跨がって使うものなのかも?と少し認識したもよう。
乗ると「後ろから押してくれ」と毎日アピールしてきました。
結局、手押し車に…。
キャスター付きの板におまるごと乗せたらノリノリでした。
お風呂前にトライ!
そうやって遊ぶことを経て、おまるに親しんだところで、次はお風呂の脱衣所に置きました。
お風呂に入る前に、服を脱ぎ、最後におむつを取って、おまるタイムを設けます。
「ここに座ってみようか」と促して、乗せて、取っ手に手を置かせます。
そして私が作詞作曲した即興のうた「おしっこちー♪おしっこちー♪おしっこちっちっちー♪yeah!」と私が歌います。
それで、終了!
おしっこが出来ても出来なくても、終わり。
「今日はおまるに座れたね!やったね!」
「一緒に歌も歌えたね!」
と声をかけて切り上げ、お風呂に入れます。
お風呂から出た後も、おまるに座って歌を歌い、すぐにおむつを履かせます。
毎日、これをするだけ!
おまるに座っておしっこが出来たらたくさん褒めてくださいね。
我が子ぶどう氏はなかなかタイミングが合わず、おまるで出ないのでお風呂に入れると、洗い場に立った途端チャーーーーっと出したり、湯舟の中で出したりします。
でも、「すっきりした?よかったね!」と声をかけて終了です。
この前、やっとおまるで出来て、たくさん褒めて一緒に喜びました。
すると、「ここでおしっこをするものなんだ」「そうすれば褒めてもらえて嬉しいなぁ」という気持ちになったらしく、喜んでおまるに乗るようになりました。
トイレトレーニングは無理しないでいい
冒頭で述べましたが、「おむつ卒業は夏がいい」とのこと。
それは、
「夏場はムレて不快感があるから早くおむつとさようならしようと子ども自身が思うようになる」
「冬のおむつは暖かいので、脱ぎたがらない」
ということのよう。
ただ、現代のおむつは「ムレない」「サラサラ」を謳っているので、大して変わらないんじゃないかなぁという印象です。
夏だから冬だから何歳だから、ということを気にして焦るのはやめて、楽しくおまる生活してほしいですね。
本人の自覚次第ですぐおむつは外れる?!
「本人の自覚次第で、おむつなんてすぐ取れちゃうのよ」と言うのを何回か聞いたことがあるんですが、それはただの精神論。
育児も保育も教育も、科学的な知識と考え方がもっと必要です。
排泄をコントロールするには、体の中で実に高度な働きが行われています。
腎臓で作られた尿は、すこしずつ膀胱にたまる。
膀胱には、一日分の尿を全て(大きなペットボトル一本分)ためることはできないから、人間は日に何度か排尿をしなくてはいけない。
膀胱は尿をためる袋の役割を持っており、大人では300~400ccの尿をがんばればためる事ができる。膀胱に尿がたまり始めても、最初のうちは特に「おしっこがたまった」という感じは自覚しない。
人によって違いはあるが100ccくらいたまり始めると少したまったかな、という感じがし始め、200~300くらいになると、そろそろたまってきたな、と感じる。
タイミングを見計らって、トイレに行くのは、大脳が判断する。トイレでおしっこをしてもいい状況になると(ちゃんとトイレにまたがって、パンツもおろしていざ、という時になってから)大脳の命令を受けて、脊髄の神経を指令が通って膀胱に伝わる。
膀胱はそこでおしっこを出そうとぎゅっと縮まり、同時にそれまで一生懸命尿が出るのをこらえていた尿道が開く。
そこで、めでたく排尿がされる。これだけの身体の仕組みがどこか一つでも働かなくなると、「排尿障害」という困った状況になる。
※引用元 名古屋大学排泄センター「チャンネルまる」
一見簡単に思えるような「おしっこをする」という行為。
脳からの指令やホルモン、膀胱の容量、溜めたり止めたりするための筋肉など。
体の色んな機能の働きが関わってきます。
自覚だの気合だのでどうにかなるものではありません。
大人は物心ついた時にはこれを無意識にできるようになっているので、子どもにも同じようにトイレができると思い込んでしまいがちです。
しかしまだまだ子どもは身体機能も脳も発達中。
できないことも沢山あるので、焦らず見守ってあげてくださいね。
漏らしちゃったらどうする??
とても大切なこと。
「トイレトレーニングを無理しないで、楽しく続けてほしい」というのは、子どものためだけでなく、保護者や保育者のためでもあります。
私の実際に関わった3歳児Rちゃんについてお話しします。
3歳児クラスのRちゃんは、ある日幼稚園で遊んでいた時におしっこをもらしてしまいました。
保育補助の先生に手伝ってもらいながら、保育室の隅っこで着替えをしてまた遊びに戻りましたが、それ以来、毎日もらすようになってしまいます。
気になった担任が保護者へ電話をすると、
「もらした日に、補助の先生から『恥ずかしい』と言われたみたいで、家でももらすことが多くなって…幼稚園バスに乗る前も行きたくないと泣いていて…」
と打ち明けられました。
そこで担任は補助の先生に話をしました。
- 子どもは遊びに夢中になって周りが見えなくなると、尿意を忘れてしまうこともある。
- 「もらしても大丈夫。怒られることはないから安心して」と子どもに伝え、園が安心できる場にしていくこと。
- 子どもにも羞恥心があるので尊重しなければならない。
着替えはみんなに見える場所ではなく、トイレなどでこっそりやること。
みんなに内緒でお着替えするから大丈夫だよ、と言葉をかけてあげること。
その翌日、Rちゃんがもらした際に、補助の先生に着替えを任せてみたところ、Rちゃんに変化が表れました。
「先生がね、内緒で着替えようって言ったの。だからおもらししても大丈夫なの!」
と、家で話していたようで、家でも幼稚園でももらすことがぱったり無くなったのでした。
補助の先生とも和解できたようで何より。
登園拒否もなくなりました。
人間という生き物はとてもデリケートで、精神的なものが排泄に大きく影響を及ぼすことって十分にあるんですよね。
色んなものが未発達の子どもは、特に配慮していかなければならないと感じた出来事でした。
…ちなみにこの保育補助の先生は、人間的にはとても良い人なんですが、「幼児教育の資格や経験が一切ない人」だったというのも付け加えておきましょう。
待機児童解消のための対策として、無資格未経験の人も保育士OK!という流れになっている現代。
乳幼児の特性に理解がない人だらけになるととても危険ということです。
トイレトレーニングを無理していると、もらされた時に親もつらくなったりイライラしたりして、つい子どもに「恥ずかしい」「だめだ」「もらすな」と言ってしまいます。
行きすぎたら手も出てしまうでしょう。
目の前のその子どもは、まだ人生始まって1ケタ!
排泄を司る脳も身体機能もまだまだ発達中!
大人のあなたとは違うんですから、焦る必要は全くありません。
我が家のトイトレつらい…と思った保護者は、無理せずおむつ使ってください。
育児は割り切れないんですよ。
まとめ
関連記事 サンタなんて本当はいないんでしょ?って聞かれたら?
ポイントをまとめます。
- おまるとともだちになる!
- とりあえず座らせて楽しく続ける
- お風呂の前後から始めてみると楽
- おしっこできたら沢山褒める
- もらしたら、叱ることはせず「大丈夫」と声をかける
- 人のいるところでもらしたら、他人に分からないように配慮する
楽しいおまる生活を!!